りれるです。
個人事業主になったばかりの新人です。
昨年はわからないことだらけではありましたが、なんとか青色申告も無事終わり、税金も無事納付し終えました。
今日は小ネタになりますが、私のような個人事業主やフリーランス、副業ワーカーにとって、1万円の領収書がどれだけ重要なのか?って話をお伝えしたいと思います。
個人事業主にとっての領収書
サラリーマンだった頃は、領収書=立替えたお金だったので、得するとか損するって話ではありませんでした。
むしろ、無くすと会社から立替えたことが認められなかったり、手持ちのお金が減ることによるお小遣いのキャッシュ・フローが悪化するだけで、はっきり言ってリスクしかなかったように思います。
ですが、個人事業主やフリーランス、副業ワーカーにとっての領収書は、ちょっと意味合いが違っていて「節税」に繋がるんです。
気になりますよねー、10,000円の領収書がどれくらいの節税になるのか?
そんなわけで、今日は10,000円の領収書のホントの価値について解説していきます。
なぜ節税になるのか?
個人事業主やフリーランス、副業ワーカーの場合、1年間の稼ぎから経費と控除分を引いた額が課税所得になります。
その課税所得に対して、所得税と住民税を支払うことになりますので、逆に言えば「課税所得」が少なければ少ないほど払う税金は減っていく、ということ。
領収書は「経費」なので、10,000円の領収書があれば、課税所得が10,000円減るので、節税になるってことです。
 りれる
りれる節税のコツは、経費と控除を最大限使うこと!
売上300万円、経費100万円、控除38万円の場合
300万円 – 100万円 – 38万円 = 162万円
→ 162万円が課税所得ということになります。
所得税と住民税
前置きが長くて申し訳ありません・・・領収書の話をする前に税金の話をしなくてはいけません。
なぜなら、10,000円の領収書がないときの課税額と、10,000円の領収書を経費としたときの課税額を比べないと、どれくらいの節税効果があるかわからないからです。
ですので、ここでは確定申告時に支払う税金=所得税と、確定申告をもとに毎月課せられる住民税について、簡単に触れておきます。
なお、他に個人事業税や消費税というものもありますが、今回は割愛させて頂きます。
所得税の計算方法
所得税は「累進課税」と言って、稼ぎに応じて税率がちょっとづつ増えていく仕組み。
稼いだ金額が多ければ多いほど税率は上がっていき、課税所得が195万円以下の場合は5%ですが、196万円になると10%の税率が掛けられます。
たった1万円多く稼いだだけで税率が倍になるなら、195万円以内に抑えたほうが良いのでは?と思われるかもしれませんが、そのへんはしっかり考えられていて、195万円を超えた分(=1万円)だけ10%が掛かるという仕組みなのでご安心を。
 りれる
りれる195万円×10% = 195,000円 ✕
195万円×5% + 1万円×10% = 98,500円 ○
こんな計算をいちいちするのは面倒なので、簡単な計算方法がありますので参考にどうぞ。
所得税の速算表
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 – 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 – 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 – 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 – 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 – 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税=課税所得×税率ー控除額
課税所得600万円の人の所得税は772,500円
600万円 × 20% – 427,500円 = 772,500円
住民税の計算方法
住民税には、所得割と均等割の2つがありますが、計算方法は非常にシンプル。
所得割は、その名の通り「所得」に対して一定税率をかけたもので、均等割は一律○○円と決まっているものです。
ただし、気をつけて頂きたいのは、その年の住民税は前年の所得に基づいて計算されているという点。
ですので、稼ぎまくった年の翌年は、住民税がめちゃくちゃ高額になることがあります(汗)
住民税の計算方法
所得割・・・課税所得×10%
均等割・・・4,000円
| 所得割 | 4% | 都道府県民税 |
| 所得割 | 6% | 市区町村民税 |
| 均等割 | 1,000円 | 都道府県民税 |
| 均等割 | 3,000円 | 市区町村民税 |
課税所得600万円の人の住民税は604,000円
600万円 × 10% + 4,000円 = 604,000円
10,000円の領収書の価値
大変お待たせしました、本題の10,000円の領収書の価値について解説していきます!
まず、10,000円の領収書があれば、税金の算出根拠となっている課税所得がその分減る、というのは冒頭お伝えしましたよね。
領収書のホントの価値は、所得税も住民税も、課税所得をベースに計算されるわけですから、10,000円の領収書があれば、支払う税金も少し減るということなんです。
今回は、課税所得が100万円、200万円、400万円、600万円、800万円の人の場合、どれくらい支払う税金が減るのか、これを計算してみましたのでご覧ください。
10,000円の領収書の価値
| 課税所得 100万円 | 所得税 50,000円 住民税 104,000円 合計154,000円 | 所得税 49,500円 住民税 103,000円 合計152,500円 | 1,500円 の節税 |
| 課税所得 200万円 | 所得税 102,500円 住民税 204,000円 合計306,500円 | 所得税 101,500円 住民税 203,000円 合計306,500円 | 2,000円 の節税 |
| 課税所得 400万円 | 所得税 372,500円 住民税 404,000円 合計776,500円 | 所得税 370,500円 住民税 403,000円 合計776,500円 | 3,000円 の節税 |
| 課税所得 600万円 | 所得税 772,500円 住民税 604,000円 合計1,376,500円 | 所得税 770,500円 住民税 603,000円 合計1,373,500円 | 3,000円 の節税 |
| 課税所得 800万円 | 所得税 1,204,000円 住民税 804,000円 合計2,008,000円 | 所得税 1,201,700円 住民税 803,000円 合計2,004,700円 | 3,300円 の節税 |
領収書はとても大事!ってこと
いかがですか?たった10,000円の領収書でも、計上しないのとするのでは、支払う税金の金額に数千円の差が生まれます。
領収書=経費なので、要は経費をしっかり計上することが大事って話なんですが、サラリーマンだった方ならわかると思いますが、領収書がないと経費として認められませんでしたよね。
クレジットカードなどの明細で代用することも可能ですが、領収書の価値が少しでも伝わっていれば幸いです。
今回の記事では10,000円の領収書を例にお話してきましたが、経費を計上すればするほど支払う税金もどんどん減っていきますので、個人事業主やフリーランス、副業ワーカーの方は、計上できるものは全部「経費」として計上するのが節税のポイントですよ。
無駄とは言いませんが、税金ほど”実感できない支払い”はありませんので、節税のためにも領収書はなくさないようにしてくださいね!
 りれる
りれる節税になるからと言って使い過ぎには注意が必要です!
あくまでも手持ちのお金が減っていくのは間違いありませんので、無駄使いには気をつけてください。
10,000円の領収書の価値は1,500円以上
まとめです。
10,000円の領収書の価値は・・・ズバリ1,500円以上!です。
売上をあげるため、事業を行うために使った10,000円は、1,500円以上の節税になります。
じゃあ100,000円分なら?200,000円分なら?更に節税になるのは言うまでもありませんよね。
無駄使いはダメですが、税金で取られちゃうくらいなら、必要なものにはしっかりとお金を使う、そして更に売上をつくる!
コレ大事ですよ!

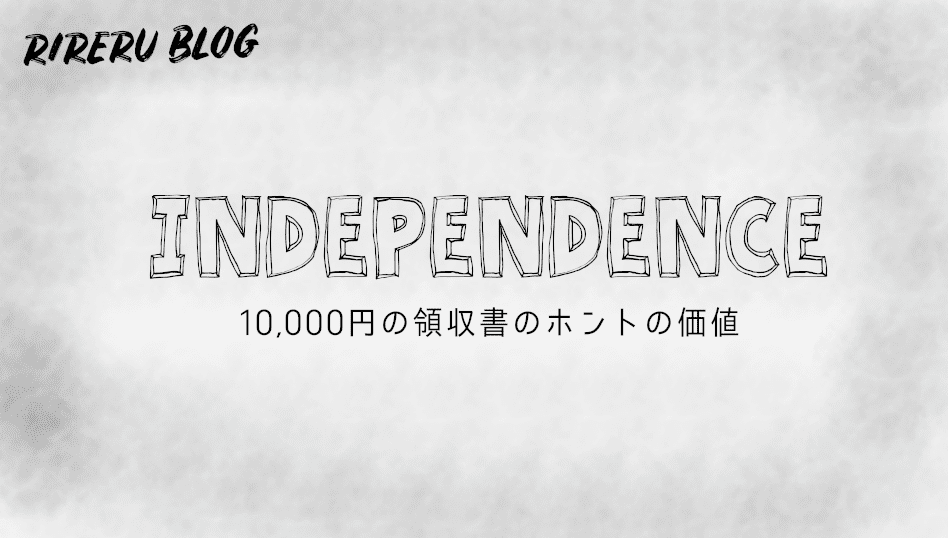
コメント